2010-02-26
談話室沢辺 ゲスト:竹田青嗣 第1回 「自由と労働」
●労働、仕事、活動に分類される人間の行為
沢辺 今回のテーマは「労働」です。竹田さんは、人間の社会の大きな流れが経済ゲームから文化ゲームへと変わっていくと言われています。僕は「労働」というものも、やがて文化ゲームと混じっていって、生きるためにするのか、楽しむためにするのか、その境目が溶けていく性質を持っている気がするんです。そこでまず、そもそも「労働」とは哲学的に言うとどういう性質のものなのでしょうか?
竹田 哲学的には、人間の活動を「労働」と「文化」と分けるのがわかりやすいです。これを私はハンナ・アレント(Hannah Arendt,1906-1975)から受け取って、なるほど、と思いました。
有名ですが、アレントは人間の行為を<労働>、<仕事>、<活動>の三つに区分しました。<労働>は人間が共同体をつくって生きていく上で絶対的に必要なもので、もし<労働>がなければ人間は滅びてしまう。しかしアレントの図式では、<労働>の必要が大きくなればなるほど人間の生の条件としては悪くなる。アレントが言う人間の条件の基本は「自由」であり<活動>がこれを担います。<労働>は自由と背反的なものです。
アレントのいう人間の生の条件はギリシアの自由ポリスをモチーフにしていますが、自由ポリスでは、市民は奴隷労働の上で何もせず遊んでいるわけです。市民は労働をしないので、自由がある。その自由があることによって、言論活動を行ない、「人間の自由は、言論活動のなかではじめて成立している」というのがアレントのイメージです。
奴隷労働の上に乗っかった自由な活動を称揚してもいいのか、という問題は残ります。しかし直感的に言って、本当に人間の自由が沸き立つための条件としては、<労働>はなるべく少ないほうがよい。もちろん、アレントのイメージひとつの概念の提示で、労働にもいろんなよい面がある。ヘーゲルやマルクスはむしろよい面を取り出そうとしています。
ヘーゲルは、労働によって人間の内的本質が外化して、形になった労働が営みになる事によって、はじめて人間の精神の本質が相互に交換可能なものになる、と言います。自由は内面として持たれているだけではなく、表現という形をとり、人間の営みの基本構造は、人間がものをつくることのなかにある、というのがヘーゲルの言い方です。有名な主奴論で、ヘーゲルは一見自由である主より、むしろ奴のほうに真の人間的自由の可能性があると言います。奴のほうが、労働、奉仕、耐えることを知り、そのことで、自然を自己化する方法をつかむからです。これは抽象的に思えるかれしれないが、かなり深い本質観取です。人間がもし労働と奉仕と忍耐を知らずにすべてを与えられて育ったら、自由の何たるか、いかにしてそれを育てつかむかをまったく知らない、わがまま息子やタカビーお嬢さまになるほかない(笑い)。
ともあれ、アレントは、そういう場面はすてて、人間の生の自由の条件を考えるために、<労働>、<仕事>、<活動>とという大きな枠組みを立てました。これはなかなかよい分け方だということがすぐ分かってくる。<労働>というのは、社会の人々の生活を支える基本要素で、それがないと社会それ自体が成り立たないものです。<労働>の条件が悪くなると財が希少性に陥るので、闘争になってしまう。したがって、<労働>の安定したシステムは、社会がなんとか戦いの契機を排除して成立しているための基本要素です。
ところが、<労働>だけだと自由がありません。そこでアレントは、単に人間を養うだけの<労働>から、人間的な自由を少しずつあげていくための工夫として<仕事>がでてきた、という言い方をしています。人間的生活を作り上げていくために、日々の<労働>の中のさまざまな工夫が、時間的にたまったものが<仕事>として成り立っていく。そして、その一番上位にあるのが、<活動>で、イメージとしては、<労働>と<仕事>という土台の上に、<活動>という人間の自由な表現活動がある。
自由ポリスは何をしていたかというと、おもに政治をしていました。政治には、自分たちの国をどうやって上手に守るか、そして、社会のなかで出てきた問題や矛盾をどう上手に調停するか、というふたつの課題があります。それを戦いによって決めるのではなく、説き伏せたり、納得したり、そういうやり方で決める場所が自由ポリスにはあった。そこで、ギリシアでは自由の領域と<労働>と<仕事>の領域ははっきり分かれていました。しかし、近代になると、はっきりとした文化が消えてしまって、<労働>の論理にすべてが覆われてしまった、というのがアレントの近代批判の大枠です。
そこでアレントの言い方を受け取って元の問題に戻ると、人間性の本質は自由の相互的な表現にあり、これは私の考えでは、ヘーゲルの「事そのもの」の考えと深く通じるところがあり、ヘーゲル的には、自由な精神の相互承認的な表現ゲームだと言えます。自由の相互承認の表現ゲームを「文化」という言葉で規定すると、<労働>はその対極にあるもので、できれば<労働>を減らしていったほうがいい、という枠組みになります。人間が<労働>の必要にしばられていればいるほど、人間的自由の余地がどんどん小さくなり、<労働>によって希少性を解決できなくなると、普遍闘争に陥る。
哲学的には、この構図がもつ原理は非常に正しいと言えます。したがって、近代社会の人間の課題を、大きなスパンでいうと、どうやって人間における必要<労働>の要素を少しずつ小さくしていくか、です。もちろん<労働>の要素を小さくすれば文化の要素が自動的に大きくなるわけではない。そこで、文化の要素をどうするかを考えないといけない。ともあれ、近代以前はどんな時代でも、ほぼ15%が支配階級で、85%が被支配階級だった。それがかなり支配社会の普遍的構造です。それで85%の人間は、ほとんどただ<労働>だけしていた。必要<労働>にしばりつけられていた。共同体の役割というのは、<労働>を上手にシステム化して整備すること。それがうまくいかないと、希少性が生じて、戦いが起こる。これがホッブズの普遍闘争原理の意味です。
沢辺 最初に僕が言った「労働」というのは、<労働>と<仕事>の区別はついていなかったのですが、いまお話を伺っていると、アレントはふたつを整理して分けていたんだ、ということですか?
竹田 その通りです。<仕事>の中には自由の要素があって、生命維持のためだけでなく、人々の生活のために役立つ便利さや楽しさをも作り出します。そして<仕事>よりももっと上位の人間的活動が「活動」です。
●近代社会における労働から仕事への展開
沢辺 こう理解していいですか? たとえばアメリカの奴隷時代、奴隷が綿花を摘んでいた。そこには移動の自由もないし、朝から晩まで働くだけ。ということは<労働>にしかならない。
しかし、綿花を摘むこと自体が嫌なことか、というとそうではなくて、「こういう摘みかたをすると5倍早くつめるよ」と誰かが思いついて、それに対して「すごいね、俺もやろう」と他者からの承認も生まれると、それが喜びになって、だんだんその綿花摘みの労働に仕事的な要素が増えてくる。
人間の近代の自由を前提にすれば、やらなければならないという意味での<労働>の要素をできるだけ減らしたり、まわりからの承認の要素を増やしていくことによって、<労働>が<仕事>に変化していくものだ、ということでしょうか?
竹田 奴隷の状態を考えると、奴隷が仕事の効率をあげる動機がありません。共同体があって、みんなで共同労働をしているのであれば、よい摘み方の工夫は<仕事>になりうる。その人は承認されるし、共同体全体が生産性を上げ、一緒に働いている人の<労働>を削減することになるし、それは大きなメリットです。
しかし、奴隷は共同体の一員というより、<労働>のための道具です。変に効率的なことをすると、もっともっと効率を、となる可能性もある。がんばったからと言って人間的承認があるわけではない。つまり、<労働>が<仕事>へと展開していくには、そのことが共同体全体にとってプラスであるような一定の自由の要素がなければいけない。はじめから<労働>にしばりつけられている場面では、少しずつよくしようとする動機が出てこないわけです。
例えばギルドのようなシステムでは、お互いに生産性を上げ合うというより、むしろ地位を守り合うことのほうが大事な要素です。新しい効率的な発明が出てくると、それまでの安定した体制を危うくしてしまう要素になる。ギルドはそうならないように職能を協同的に守るものです。もちろん、その中でも一緒に働いている人の<労働>を楽にする多少の工夫はありましたが、職能共同体自身をゆるがす工夫はそれほど必要とはされなかったはずです。つまり、アレントの言うような<仕事>が本質的に展開するためには、社会システム自体が多少自由になっていないといけない、という条件があるわけです。
役割関係や階層関係が固定しているところでは、<労働>が<仕事>の喜びになるのは、非常に限定された形でしか起こらないでしょう。アレントも、「近代が進展していくなかでさまざまな仕事が起こってきた」と言っていて、<労働>が<仕事>になるのは、それがみんなとシェアでき、みんなの生活を豊かにするという前提の上でなんですね。
ところが、アレントによると、近代が進むと、<労働>の論理が普遍化されるので、<仕事>をしてもそれ自体がお互いの競争になる。つまり、ひとつよい<仕事>があると、すぐ他の人間がその真似をする。そうするとあとは能率を上げてゆく競争がはげしくなって、全体としては結局<労働>の論理がひたすら強化されていく、いうことになり、それが自由には展開していかない。それが近代だ、と。それはある意味当たっています。
近代社会というのは、ピラミッド型だった社会を各人が対等な丸い形にして、固定的な階層関係、役割関係を解体した。そのことで、人間の<労働>が効率だけでなく創意や工夫を取り入れ、<仕事>になっていく可能性を持ったわけです。その点では近代社会は評価できるのだけど、一方で近代社会競争による経済なので、誰かが効率をあげると、もう一方もそれに追いつかないと没落していく。だからだれもが負けないように効率をたえず上げつづけないといけない。そのために、<労働>が自由を含んだ<仕事>に転化するや否や、あらゆる工夫が、単に新しい質の<労働>になってしまう。すると、絶えず<労働>の効率化が行われるだけで、結局、そこでは人間の自由の要素は死んでしまうわけです。
エンゲルスが描いたイギリスの労働者の状態を見ると、技術力と生産力はどんどん上がっていくけれどもそれが労働者の労働の強度をますます上げるようなシステムになっていることがよく分かる。何かを発明した人には特許などで儲けが返ってくるけれど、<労働>の絶対的な効率競争になってしまい、すべての人間が労働時間の下に従属させられる。そうなると、自由の条件を含む<仕事>の余地がどんどん小さくなってゆくわけ。またひとつの社会がそうそう労働効率社会になると、国家間では競合が激しいので、どの国もまったくおなじ状態になる。どの国もいかに早く資本を蓄積するか、いかに効率的にそれをできるかという話になる。本来、<労働>の中で常に新しい工夫を見出すことは、発見のエロスと、見出したことよって生産性が上がり、人間の生活に資するはずというふたつの意味を持っていた。ところが、それは最終的には合理性追求の果てない競合の運動のなかに巻き込まれ、なんのために<労働>の工夫があるのかわからなくなる。それが近代社会の<労働>の状態です。
●競争原理に打ち消された人間の自由
沢辺 ミクロ的に見ると、例えば昔だったら著者にゲラを手渡ししていたものが、いまは宅急便やメールになって、移動にかかっていた時間は確実に減っている。けれども、トータルな労働時間が減っているかというと、新たなサービスや新たな労働が増えたので、結果的には全然減っていない、というようなことでしょうか?
竹田 生産性を上げるための一切の工夫や創意は、結局、競争の原理が強く働いている限り、決して人間の生活に余裕をもたらさない、というのが、20世紀における先進国の一つの大きな経験だと言えますね。二十世紀後半、つまり大戦後から20年ほどは、先進国は例外なく7%前後経済成長をしていた。これは10年たつと豊かさが倍近くになるということです。ところが実際人間の生活はどうかと言うと、たしかに客観的な数値としては一定の豊かさを達成したことは認めなくてはいけない。しかし、人間の心意としては、ほんとうに高度成長によって多くの人間が未来に希望を描けたのは、おそらく1970年代までで、そのあとはもう社会の先行きの見通しはどんどん閉塞していった。いまは世界的に、すべての先進国が高度成長を続けるような可能性は、どこにもない。その理由はちょっとあとで言うけれど、ここではふたつのことがある。ひとつは、生活の豊かさの感覚は、「社会がこういう風によくなっていく」という持続的成長のビジョンのもとでだけ可能であるということ。もう一つは、豊かさの感度は、常に相対的なものだということ。つまり、たとえば40年前とくらべると、人びとの所得はたしかに倍増以上になっているし、また当時は考えられなかった週休二日制がほぼ実現している。しかし、それを“豊かになった”と感じるのは、一定の世代だけで、今の若い人にとっては、もうそんな感度はまったくない。わたしはそれを、欲望の底板の不可逆性と言っているんだけど、豊かさの感覚は、生活条件のたえざる上昇ということ、それが持続的に続くという展望、という二つの条件を必要とするわけです。いま先進国の所得は貧しい国の数十倍もある。しかし、われわれはそれを比較して見るとき以外は、生活の豊かさというものをほとんど感じてはいない。可能性ということが大事なんです。
沢辺 主婦労働は便利さが楽につながっていない典型ですよね。掃除機も洗濯機もできて、機械化によって圧倒的に効率的になったはずなのに、主婦の労働は楽になっていない。これを調査した社会学者がいるんですが、昔だったらお茶わんなんてお茶ですすぐだけで、洗剤をつけて洗ったりしなかった、と。洗濯だって、いまは毎日洗ってますが、僕が子供の頃は、上の服なら三日は着てた。だから、確かに生活全般はより清潔になっているけど、主婦労働は一向に楽になっていない、ということですよね。
竹田 考えなくてはいけないのは、いつも言っていることですが、近代は人権の確保という点で「自由」を解放したいっぽうで、社会の全体が、経済競争の論理を強めてきた。生産性はぎりぎりまで追求されてどんどん上がってきたけれど、そこで、格差、負け組感覚、余裕のなさ、希望のなさというものが、じわじわ大きくなっていると多くの人が感じている。つまり、万人の生活に余裕を与えるという近代社会の本義は、競争原理によって打ち消されてしまって、昔より悪くなったとまでは言えないとしても、少しずつ進んでいるという感覚はまったく存在しない。
競争の原理が強く働いているかぎり、国家どうしは、生産性の効率を上げることに必死にならざるをえない。つまり、国家どうしの競争原理をどう緩和してゆくかという工夫がない限り、資本主義はどこまでいっても<仕事>や<活動>の領域は拡大せず、人間はどこまでいっても必要<労働>にしばりつけられ、そこから出ることができない。近代社会の意義の中心をもう一度はっきり自覚しなければならない、というのが私の言いたいところです。
もちろん近代社会にはいくつか大きな課題があって、ひとつは国家間の普遍闘争です。近代国民社会は国家の内側については、徐々に各人が権限を委譲しあう人民主権を打ち立てましたが、国家どうしではそのまったく原理が働いていない。ゆえに近代社会は国家間の普遍闘争を抑制する方法をはじめから持っていなかったのだければ、それでも先進国どうしの普遍闘争は第二次大戦で実質的には終わりました。東西対立は潜在的に続いたけれど、それも現在は終焉して、いまのところ先進国どうしでは戦争をする理由はなくなってしまった。
しかし、代わりに経済競争が残っています。過剰な経済競争をどう制御するかという次の課題をはっきり自覚しない限り、近代の理念である「人間の自由」は実現しない。戦争についていうと、国民国家が戦争共同体として武力的な競合関係にあるあいだは、大衆消費はありませんでした。どんな国家も飛躍的に増加した生産力のほとんどを軍備に費やさねばならなかったからですね。たとえば、列強国どうしで、軍艦の持ち分について条約をつくったりしている。ともあれ、その後、第1次大戦が終わったときに、これに参加しなかったアメリカで消費社会が現われてきた。軍備に膨大な予算をまわさなければ、一般福祉に回るという象徴的な例です。
第2次大戦以降、アメリカはむしろ自由国家を請け負って、ソビエトと軍備競争をやったけれど、それでも実際に戦力を使うことはなく、もっと本格的な大衆消費状況がアメリカで起こり、その状況は先進国にも広がっていった。敗戦国の日本ですら、戦後10%を超えるような高度成長をみたわけです。これは、近代社会の本義からいうと、まず大きな一歩だと言える。ほとんどの一般大衆が労働だけで生きるのではなく、「消費」し、享受できるようになったわけ。
次に起こった大きなエポックは週休二日制。これはドイツから始まって先進国で広まっていった。理由は第二次大戦後、日本やドイツ、イタリアも含めて進んだ国がどこも民主国家になったからです。民主国家になると、戦争もう難しくなる。もちろん専制的国家で好戦的な国がある限り、民主国家も対抗上戦争する。民主国家では基本戦争の決定はきわめて難しくなる。
それからまた、先進国が民主化していくと、はじめは支配階級、富裕層を代表していた政治権力は、必然的に中間層、中産階級の意向を受け取らざるを得なくなってくる。要するに、「一般福祉」をそれなりに配慮しなければ、政治権力として支持されなくなってくる。つまりどんな国家も社民化してくるわけです。これは必然で、20年くらい前からヨーロッパがどんどん社民化し、一般福祉が上がり、週休二日制という労働時間の短縮もその結果の一つですね。つまり、大衆消費状況と労働時間の短縮のふたつは、近代市民国家にとってそれが前進しているかいなかの大きな指標です。
●資本主義の限界
竹田 しかしそのあと何が起こったかというと、1980年代ほどから、先進国の経済成長が落ち込んできた。戦後、ほとんどの先進国が大きな成長を続けてきた理由は、十九世紀から二十世紀にかけて資本主義の弾み車=モーメントがあって、それは石油の発見と、電気その他科学技術の大きな革命があったからだと思います。でも、その弾み車もいま使い切って、もう先進国が、大戦後の20年のような経済成長を続ける要素はなくなってしまった。これは、おそらく新しいエネルギーの発見と大きな技術革命が起こらないと、世界規模で資本主義の回転がどんどん大きくなるということは難しいわけ。こさまでの感覚は、自由競争をどんどん活性化して、資本の回転を高めれば、生産力はますます上がり、経済成長も続くだろうとという感覚があった。格差は、ケインズ的方式で適度に再配分をやっていれば、結局は、人びとの一般福祉も持続的に上がっていくだろうと考えていた。しかしこのパースペクティブはもうありえない。
それから、二番目三番目の中進国であり、人口巨大国である中国とインドが、先進国に変わって新しい要因で経済成長を上げていることは、また大量生産と大量消費という資本主義の宿命的な弱点を大規模な形で浮上させた。さらに、人口爆発が、さっきいったように貧しい国の統治の不安定と先進国の食料生産の技術という要素で続いている。簡単にいえば、中国がもし日本なみの生活水準に達したら、このままの成長率でいくとあと20年ほどでそれに近づくが、資源的に、地球がもう一つ必要になるという試算がある。中国だけの話です。つまり、資本主義が大量生産、大量消費を続ければ、もう間もなく先に絶対的希少性の問題が現われる。それはここ3、40年の話です。希少性が現われると、現在人類は核をもっているので、カタストロフィ的戦争になる可能性が非常に高い。これが現在の資本主義の進んでいる水路です。タイタニック状況です。
さっき言ったけれど、資本主義はいろいろ弱点もあるが、基本の最大の意義は、普遍消費を拡大し、人間の自由の条件を少しずつ上げてゆく点にある。必要<労働>」の契機を縮減して<活動>の領域を拡大する。それが人間の自由の基礎条件だというのがアレントの展望ですね。たしかに二十世紀の資本主義は、紆余曲折をへながらも少しずつはその道すじを進んできた。ところがいま人類がぶつかっているのは、ここままの進み方で普遍消費が進めば地球がパンクするという破局的事態です。いま資本主義が進んでいるコースをはっきり変えるほかはない。哲学的なスパンではそのことがはっきり言える。
沢辺 いまのところでいうと、資本主義が石油などのエネルギーという弾み車を使いながら成長してこれたことで、多くの普通の人の消費と自由が拡大してきた、ということですよね。でも僕はいまの日本の状況を見ると、日本の民衆の消費のスポンジは、もうすでにたっぷんたっぷんなんじゃないかと思います。
竹田 そのとおりで、考え方として、成長を回復することで矛盾を解決するという発想はもう効かなくなってきた、むしろ偏りや格差を上手に調整するという方向で考えるほかはない。それから、一般民衆が十分な消費をもてるようになったのは先進国だけで、そのあいだに、貧しい国の人たちの生活がますますきつくなってきた。注意すべきはその大きな原因として、この四十年のあいだにまずしい国で人口が爆発した。また、その増大した人口を養ってきたのは明らかに先進国の技術力です。先進国の生産性と技術力が爆発的に増大したことが、逆に、世界の人口爆発をささえてきたわけです。その結果、惨めな状態の国の人口が、また急激に増えてきたんですね。
次回へ続く
プロフィール
竹田青嗣(たけだ・せいじ)
1947年大阪生まれ。哲学者、文芸評論家。
早稲田大学政治経済学部卒業。現在、早稲田大学国際教養学部教授。
『低炭素革命と地球の未来』発売中

『低炭素革命と地球の未来』─環境、資源、そして格差の問題に立ち向かう哲学と行動
著●竹田青嗣、橋爪大三郎
定価1800+税
ISBN978-4-7808-0134-7 C0036
B6判 / 192ページ /並製
[2009年09月刊行]
目次や著者プロフィールなど、詳細はこちらをご覧ください。



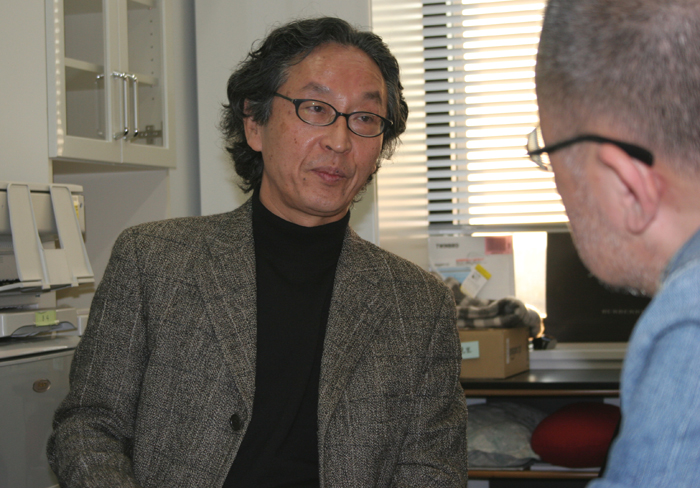

[...] 第1回「自由と労働」 [...]
[...] 沢辺 その当時は、竹田青嗣(哲学者。早稲田大学大学院教授)さんはまだ早稲田で教えてないよね。まだ明学(明治学院大学)だったよね。 [...]
[...] 〈strong〉沢辺〈/strong〉 その当時は、竹田青嗣(哲学者。早稲田大学大学院教授)さんはまだ早稲田で教えてないよね。まだ明学(明治学院大学)だったよね。 [...]
[...] 沢辺 その当時は、竹田青嗣(哲学者。早稲田大学大学院教授)さんはまだ早稲田で教えてないよね。まだ明学(明治学院大学)だったよね。 [...]